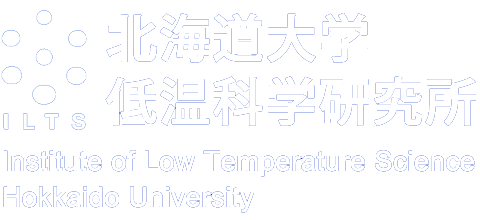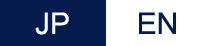一般・学生向け
低温研で活躍する学生

本田 茉莉子
海洋・海氷動態分野/環境科学院 地球圏科学専攻 D3
写真:オホーツク海にて XCTD(投下式塩分水温深度計)観測を行う様子 (2023年9月)。
低温研を知ったきっかけは?
私は学部生のときに北大理学部地球惑星科学科に在籍していました。4年生で研究室選びをするときに、まず環境科学院の大気海洋物理学・気候力学分野に配属され、さらに分野担当教員から指導教員を決める際に、低温研の大島慶一郎先生の研究室に所属することになりました。当時は自分がどんな研究がやりたいのか、研究とは何なのか、すべてが不透明でしたが、普段の生活と全く異なる環境である極域海洋に、ほんの少しの興味を持ったことがきっかけでした。
低温研で今どのような研究をしていますか?
オホーツク海の海氷と海水の変動に関する研究をしています。オホーツク海の海氷は主に北西部で生成し、季節風と南向きの海流により南部へ漂流して、北海道にも接岸します。このような海氷の生成・移流・融解過程とその変動が、海洋にどのような影響を与えるかを、観測データを解析して調べています。たとえば、春季のデータを用いて、海氷が融解した直後にできる低塩分層から融解量を推定し、オホーツク海南部の海氷融解量の減少を示しました。また、オホーツク海北海道沿岸を流れる日本海起源の暖流(宗谷暖流)域の温暖化も観測データから示しました。冷たく寒いオホーツク海は、生物資源が豊かな海でもあるため、海氷や海水の物理過程と生物地球化学過程の関わりについても今後調べていく予定です。
大学院進学を決めた理由は何ですか?
学部から修士課程へは、大学院生への漠然とした憧れのもと、あまり深く考えずに進学しました。修士課程1年の2月にオホーツク海の海氷観測に参加させていただき、海氷を自分の目で見たことで、いま目にしている海氷はどこから来たのか、これからどこに行き、どのように融解し、海や大気に何をもたらすのか、と疑問に思いました。修士課程ではこれらの疑問を回答するに至らなかったため、博士後期課程進学を決めました。
なぜ今の研究をやろうと思ったのですか?
ひとつは、オホーツク海はユニークな海であることを知ったからです。オホーツク海は北半球で最も低緯度に海氷が分布する海で、中緯度に位置する日本、に接する海が極域の性質をもつという特徴に興味を持ちました。また、オホーツク海の海氷は冬~春のみ存在し、夏にはすべて融けきることから、熱と塩のダイナミックな季節変化があることも印象的でした。もうひとつは、低温研の研究者がオホーツク海研究を長年推し進めてきたことによります。観測データがほとんどなかった時代に、海洋観測航海を計画・実行し、結果として実態をつかんだ先達が身近にいる環境は、研究初心者の自分にとって、研究の姿勢や実践的な知見を深く学ぶ貴重な機会であると考えました。
研究のおもしろい点はどこですか?
数字の羅列である観測データから、未発見の事実を発掘するのがおもしろいです。また、いろいろな切り口でデータを解析したうえでひとつのことが解釈できるとき、楽しいと感じます。ほかには、プログラミング言語を利用して図を描くことも没頭できる作業で、たまに意味のありそうな図が描けると嬉しくなります。たくさんの方に助けていただきながら、現場で自ら観測データを取得する大変さとやりがいを知ることもできました。
札幌での暮らしはいかがですか?
私は大学進学時に東京を離れて札幌に住み始めました。札幌は、おいしい食材がすぐ手に入る点と、周囲に雄大な自然がある点が気に入っています。お米、小麦、乳製品、お肉、魚介類、野菜、お酒など、食と自然が直結していて飽きません。登山や温泉巡りにも適していて、夏と冬で景色が全く異なることも魅力だと思います。北大構内の低温研付近では、季節を問わずエゾリスが走り回っていて、ついカメラを向けてしまいます。
これから大学院進学を志す後輩へのアドバイスは?
「とりあえずやってみる」精神で様々なことにチャレンジするといいと思います。やる前はなんだか難しそうと思っても、意外と自分に合っている事柄が見つかることがあります。もし見つかったら、長期的にどうにか継続していくと、日々が充実する一方で自身の能力につながります。自信と謙虚さのバランスも重要です。また、新しいことを始める際は、安全性の確保、十分な息抜き、周囲への相談を忘れずにしましょう。

写真:上空から撮影したオホーツク海南部の海氷 (2022年2月)。
(2025.7)